
先日、「旅人」と「観光客」の違いについての記事を書きました。
この二つは明確に意味が区別されているわけではありませんが、多くの人が違いがあると考えています。
前回はポール・ボウルズの『シェルタリング・スカイ』に登場する「旅人は帰らないこともある」というセリフから、両者の違いを考えました。
» 旅人と観光客の違いを考える。ポール・ボウルズ『シェルタリング・スカイ』
「帰らない」というセリフから「家」という概念に着目し、旅人は「家」を失う可能性を秘めている状態のこととしました。
そしてもう一冊、次は哲学者の言葉に耳を傾けたいと思います。
旅人と観光客の違いを考える。マルクス・ガブリエル『なぜ世界は存在しないのか』
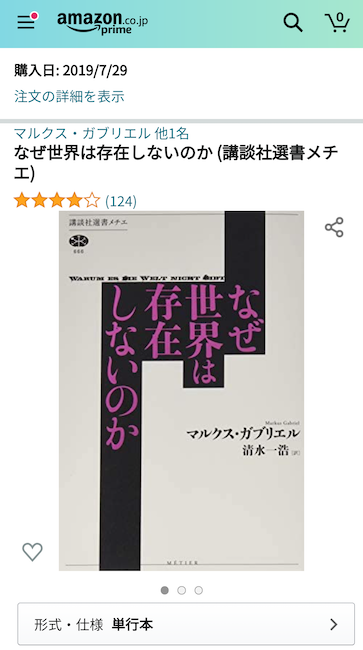
ドイツ人の哲学者であるマルクス・ガブリエルの2018年の著作に『なぜ世界は存在しないのか』という本があります。
著者はこの本の中で「意味の場」という概念から、唯一絶対の世界は存在しないことを証明していきます。
ガルブリエルは、この世界のあらゆるものは、なんらかの「意味の場」に属してると言います。
「意味の場」とは?
ガブリエルの哲学において、存在は下記のように説明されます。
存在すること=なんらかの意味の場に現象すること
『なぜ世界は存在しないのか』
何かがこの世界に存在するためには、なんらかの「意味の場」に現象しなくてはならない。
「意味の場」に現象することでこの世界に存在しているということができる、と。
「意味の場」と「現象」はガブリエルの哲学でキーとなる言葉です。
ガブリエルは、「意味の場」に現象することをこのように説明します。
ひとは国民として何らかの国家に所属していることがありえます。3という数は自然数に属していますし、分子は宇宙の一部をなしています。このように何かが何らかの意味の場に属しているわけですが、その属し方こそが、 その何かの現象する仕方にほかなりません。
『なぜ世界は存在しないのか』-p108
国家に国民として所属することで、国民として現象し、この世界に存在していると言えるようになります。
国家という「意味の場」がなければ、国民としての現象はなく、国民はこの世界に存在しないことになります。
例えば、目の前にある「焼き物の湯のみ茶碗」を「飲み物を飲むもの」と考えるか、「陶器の置物」と考えるか、「素粒子の集積」と考えるかで、ものの意味は異なってきます。
器は「飲み物を飲むもの」という「意味の場」に湯のみ茶碗として現象することで(そのような仕方で)、この世界に存在しているということになる。
「陶器の置物」も同様に、茶碗を置物として扱う意味の場に現象することで、置物として世界に存在することになるわけです。
意味の場とは、このように”何らかの特定の対象が、何らかの特定の仕方で現象してくる領域です”-p102とガブリエルは説明します。
現象とは、この世界での役割や意味のようなものと考えると分かりやすいかと思います。
前例の「焼き物の湯のみ茶碗」は現象する仕方によってその役割が変化しています。
そして、その現象の仕方はいつも同じではないし、同じものも別の仕方で意味の場に現象してくるといいます。
決定的なのは、何かの現象する仕方がいつでも同じわけではないということです。すべてが同じ仕方で現象するわけではありませんし、すべてが同じ仕方で何らかの意味の場に属するわけでもありません。
『なぜ世界は存在しないのか』-p108
以上が、簡単な「意味の場」の説明ですが、おそらくここまで聞いた人はこう思ったかもしれません。
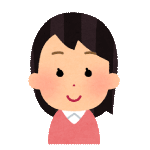 ここまでの話を聞いた人
ここまでの話を聞いた人申し訳なく思いますが、これが今の私なりの精一杯の説明です。
ただ、ガブリエルは意味の場の哲学を解説する中で、旅行についても触れています。
その文章が「旅人」と「観光客」の違いを説明する上で良いと思うのです。
意味の場から旅人と観光客の違いを考える
次の文書が著作内で旅行について触れた文章です。
商業主義的な旅行で問題になるのは、そもそも旅行で はなくたんに気候条件のよいところに場所を変えて過ごすとか、絵葉書向けの写真を撮るといったことにすぎません。
『なぜ世界は存在しないのか』-p255
まず、観光客としての説明として上記をとらえてみます。
絵葉書向けの写真を撮るということは、既に知っている情報をなぞりながら現地を旅行しているということになります。
観光地として整備された場所を、事前情報に沿って移動していることになる。
こうした自分たちの慣れ親しんだ環境からはみださない態度を観光客的な態度と考えることができます。
自分たちの属する「意味の場」や、自分たちのもつ「意味の場」から離れることのない旅行です。
これにたいして本当の旅行では、なじみのない物ごとに触れる驚きを体験するものです。わたしたちとは異なる環境に暮らす人たちがしている多くのことは、わたしたちには疎遠に映る。ほとんど意味がわからないことさえある。 わたしたちは、 その人たちの振る舞いを理解するように努めるほかありません。つまり、わたしたちは突然にして異なった意味の場に置かれ、そ の意味の場の意味を探求している状態にあるということです。
『なぜ世界は存在しないのか』-p255
ガブリエルが「本当の旅行」と表現する旅行では、異なった意味の場に置かれ、意味の場の意味を探求している状態にあると言います。
私はこれが旅人的な態度だと思うのです。
つまり、それまでの自分たちの「意味の場」から離れ、別の「意味の場」と出会うことです。
意味の場の意味を探求する状態というのは、異文化や価値観の異なるもののことを考え、受容する可能性を示す態度だといえます。
前回の『シェルタリング・スカイ』の論考の中で、元の「家」に帰らなくなるかもしれない態度で旅行することを旅人的と表現しましたが、ガブリエルにおける『意味の場』も同様に受け取れます。
元の『意味の場』の意味を見失ってしまうかもしれない態度で旅行にでることが、旅人的な旅なのだと思います。
私は旅行の期間は関係なく、例え数日であろうとも、こうした気持ちで旅行に望めば、それは旅なのだと考えています。
事前情報をなぞるだけだったり、気候の良いリゾートや都市を移動するだけではなく、予測不可能性に身を委ねて、元の「意味の場」や帰るべき「家」を失うかもしれない態度で、旅行にでることが旅なのだと思うのです。
少し長くなりましたが、以上で第二回目の論考とします。
まとめ
マルクス・ガブリエルは著作の中で、唯一絶対の世界は存在しないことを証明します。
世界が存在するには、世界もまた何らかの「意味の場」に属し現象しなくてはなりませんが、何らかの「意味の場」に属する世界は、唯一絶対の世界ではなくなると。
それはあくまでも、その「意味の場」に属し現象する世界ということになるからです。
だからこそ、世界は存在しないのだと。
こうしたガブリエルの哲学は新しい実在論と呼ばれ、世界の哲学に新しい潮流をうみました。
今日はそんなマルクス・ガブリエルの「意味の場」から旅人と観光客について考えました。
次回は上温湯隆の『サハラに死す』から、旅へと出てそのまま帰らぬ人となった人の物語に触れてみたいと思います。
ねづ店長のワンポイントアドバイス
![]()
僕もまた「ねづみブックス」という意味の場において、ねづ店長として現象しているから、この世界に間違いなく存在していると言えるんじゃないかな。
